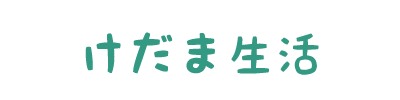2017年頃から2020年2月まで2匹の愛犬パピヨン(2001年生まれのチヨ(永遠の18歳8ヶ月)・2002年生まれのたみ(永遠の16歳11ヶ月))の介護をしていました。
チヨは気管虚脱や胆泥症、嚥下運動の低下、会陰ヘルニア(膀胱脱)、老齢性の発作など主に加齢による機能の低下や疾患を抱えながらもいつも気合十分。
2020年2月11日に亡くなる前日の夜までしっかりご飯を食べて、チヨらしく旅立ちました。

チヨはたみのような認知症にはならず最後までしっかりとした意思を持っていましたが、歩行や食事など生活の介助は必要で、介護中はほんの数分洗濯物を干すにも神経を尖らせるほど気を抜くことが出来ませんでした。


たみは3年2ヶ月にわたる慢性腎臓病の治療の他、脳疾患や認知症も発症したため晩年は24時間体制の介護。
若い頃からずっと素直で大人しいたみちゃんがここぞとばかりに自我を爆発してくれたので、一生分のワガママを今言ってるんだなと大変ではありますがすごく嬉しかったです。

たみの持病の腎臓病は最後まで悪化することなく、とても穏やかに老衰で旅立ちました。

そんな2匹が教えてくれたたくさんのことは、私の人生の宝物。
介護が始まった当初はそれが認知症の初期症状ということも分からなかったり、本には書いていないような症状が現れたり、もっと早くから対策していればもう少し快適に過ごさせてあげられたかもしれないと思うこともあり、当時の私が犬たちの少しの変化を不安に思い検索した時に目にすることが出来ていたらと思う記録とここに残しておくことにしました。
これから老犬介護を始める飼い主さん、今まさに老犬介護の壁の前で途方に暮れている飼い主さんの暮らしのヒントになりますように。
私はおそらくとても変態なので、老犬介護で寝られなくても、お風呂に入れなくても、引きこもりすぎて近所の奥さんから生存確認されても全然苦ではありません(普通の主婦業とお財布は辛いです)。
ですが正常な人間にとっては昼夜問わず夜鳴きに悩まされたり、夜通し眠れなかったり体のジタバタが止まらなくて犬も困っていそうなのにどうしてあげることも出来なかったり、ご飯を食べなかったり、病気で具合が悪かったり…睡眠不足・不安・疲労・金銭的な問題など色々な要因が重なって逃げだしたくなることもあるのではないかと思います。
老犬介護は教科書通りにはいきません。
1匹1匹、抱えている疾患も、性格も、体格も何もかもが違います。
例えばこれは介護に限らず他の病気の治療の体験談でもありますが、

ご飯を食べられなくなったらシリンジで与えればいいんだよ
とアドバイスされた場合、たみならすんなりとシリンジ食に移行できますが、チヨは無理。
絶対無理。



ム~リ~!!!
と暴れて絶叫しておまけに喉にご飯を詰まらせてしまうかもしれません。
というわけでこのサイトに書いてある事は、私が育てた私の犬であっても、たみには良くてもチヨには絶対無理な介護方法、まさにオーダーメイドの介護の記録です。
なのでこのまま試してみるもよしアレンジしてみるもよし、「こんな方法もあるんだな」と隣の老犬介護をちょこっと覗いた気分で読んでいただければなと思っています。
やってみたけど無理だった…なんて、落ち込む必要はありません。
あとひとつだけ伝えておきたいのは、寝るのも休むのも好きなものを食べるのも美容院や映画に行くのもお金を稼ぐのもあとでいくらでも出来るから、どうか少しでも後悔のない毎日を送ってほしい。
明日は当たり前には訪れません。
辛い日もあるかもしれないけど、今しか触れられない宝物を大事に大事にしてほしいなと思います。
ちなみに美容院行かないとどうにもこうにも頭がもっさり…という時は、「サローネヘアカットブラシ」が便利です。
「ヘアカットモンスター」もなかなか良かったです。
私、老犬介護卒業したのにまだこれでセルフカットしてます。
最初に読んでほしい記事
老犬介護当時にやっていたTwitterアカウントのツイートをnoteにまとめています。
私たちにとってとても大切な記録でもあるため一部有料にしています。


認知症はある日突然始まるものではありません。
あれ?と思う事が増えて、完全に認知症になってからあの時のあれが始まりだったのかと後から気づく。
以下の記事にたみの認知症の始まりについてまとめました。


犬の介護用品は犬用として商品化されているもの以外にもベビー用品や日用品で代用したり、手作りをすることも可能です。
もしかすると商品に頼ることに抵抗がある方もいるかもしれませんが、絶対に便利グッズは取り入れるべき!
ワンオペ介護の私にとっては家族よりも便利グッズが助けてくれたと言っても過言ではありません。
それにいずれ必要になるものならば躊躇せず早めに買っておくと、いざ介護となった時に慌てずに済むかなと思います。


足が不自由になったら、歩行を補助する道具が必要になります。
絶対必要というわけではありませんが、寝たきりにするのではなく、たとえ歩けなかったとしても四本足で立った姿勢に起こし、内臓を正しい位置に戻すことはとても重要。
チヨは後ろ足だけが不自由で、立ち上がる度にハーネスをつけさせてくれるような大人しいおばあさんではないので、24時間つけっぱなしにしておける布製の後ろ足用補助ハーネス(チヨベルト)を作りました。






たみの場合は寝たままでヒャンヒャン鳴いたりジタバタ暴れる時は、パニックやわけも分からず騒いでいるのではなく、「立って歩きたいのにどうにもならない」という状態のことがほとんどでした。
車椅子の購入も検討しましたが、早急に必要だったことと、たみは首が後ろを向いてグルグル回りたい、顎を絶妙な高さに置いて立ったまま寝たいという希望があったので、塩ビパイプで歩行器(たみカー)を手作りしました。


また、チヨも晩年は足が弱ってしまったのでチヨカーを作り、塩ビの曲げ加工まで施して完璧な仕上がりになり、食事の際の支えとして大活躍しました。
歩行器は本当に作って良かったと思います。
食事がうまくとれなくなったら、「強制給餌」というシリンジで流動食を口に流し込むという文章で読むととても嫌な印象を受ける食事の介助の方法がありますが、私はこれをお食事サービスと呼んでいます。
たみの場合はシリンジを嫌がらずに受け入れてくれたので、シリンジを使うことにより腎臓病の療法食を完璧に与える事が出来ました。
チヨの場合はシリンジで飲ませようだなんてしたらまさに「強制給餌」になってしまうので強要はしません。
ですが嚥下運動が低下して喉に食べ物を詰まらせやすいので、流動食を自分でお皿から飲んでいます。


寝たいのに寝られない!!!と本人も困って泣くことがあります。
そんな時はおねんねサービスしましょう。


老犬介護をする上で、さっと手に取れるところに参考になる本があるととても役立ちます。
私がおすすめしたい老犬介護の本は、「イヌの老いじたく」「老犬生活 完全ガイド」の2冊。
老犬介護卒業してから発売されたので読んではいませんが、ちょっとお高めなものの良さそうな一冊「高齢犬・高齢猫の「本当に困った! 」が解決 対応策がわかるハイシニアケア」もいつか読んでみたいです。


以上、特に読んでおいてほし老犬介護に関する記事のご紹介でした。
老犬介護の記事は他にもありますので、以下からピックアップしてみてください。
老犬介護情報新着記事一覧
-



老犬の最期の症状【終末期~看取りの兆候と飼い主に出来ること】
先代のチヨたみを看取って4年以上経ちました。これまで詳しいことまで振り返ること… -



老犬の胃拡張の症状と予防・治し方(マッサージ・薬など)
食べないという悩みは一切なく、便秘もしたことがなかったチヨ(パピヨン♀2… -



後悔の少ない最期のために飼い主が出来ること【チヨちゃんの旅立ち】
チヨは18歳8ヶ月(18歳9ヶ月まであと1日!)で旅立ちました。今まではっきりと書か… -



末期がんの父の在宅介護から学んだこと【犬猫たちに活かしたい】
チヨたみの介護が本格的に始まる少し前に亡くなった祖母(認知症・大腿骨骨折)が… -



猫の投薬による食道炎に注意したいと思った話(犬も)
私の話なのですが…先日、朝起きると食道の辺りが重苦しく、何かが詰まったような感… -



「犬の飼い主」ではなくなった私は、これからをどう生きるのか
19歳の7月、私は初めて「自分の犬(チヨ)」を飼った。 38歳の冬、私は初めての自… -



ビオピュア犬用マーゲンダルム・エアクランクンゲン【胃腸が弱い犬に】
同居犬たみが腎臓用療法食を美味しく食べたビオピュアの胃腸用「マーゲンダルム・… -



犬の服は背中開きが着せやすい【老犬介護に点滴に大活躍】
犬の服って被せて着せたりお腹側にボタンやファスナーがついているタイプが多いの… -


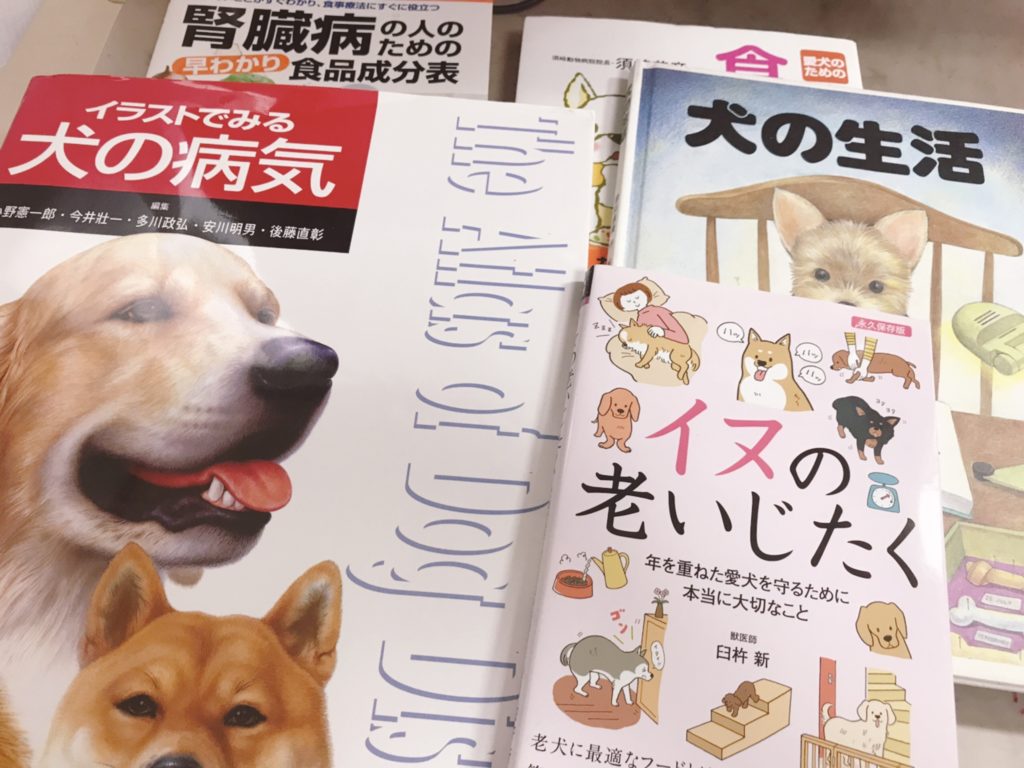
犬の飼育や老犬介護に役立つ本おすすめ一覧
犬の飼育や闘病、老犬介護をする上で、ある程度の基礎知識や情報があるにこしたこ… -



【グリーフケア】ペットロスの乗り越え方…なんて分からないけど耐えられそうな気がする
ペットロス…うん、私はペットロス。 たみちゃんロス。 10日前に愛犬たみが亡くなり… -



犬の歩行器(四輪)の作り方【塩ビパイプの曲げ方など】
苦節1年くらい?初代チヨカーを含めると1年半くらい? 遂に老犬用4輪歩行器「新チ… -



愛犬が自宅で亡くなった時にしたこと【ケア・手続き・お別れの品など】
大好きなたみちゃんが亡くなり、明日はもう初七日です。 思い出してはウルウルして… -



腎不全闘病3年2ヶ月、老衰で穏やかに旅立ちました。
2019年5月30日14時頃、私の愛犬たみが16歳11ヶ月29日で息を引き取りました。 13歳… -



パピヨン18歳、元気の秘訣は気合と食欲【日常のケアと介護】
我が家の美長老チヨ、5月12日に18歳の誕生日を迎えました! いやーめでたい! って… -



老犬が徘徊して寝ない時の対策【我が家のおねんねサービス】
犬が高齢になり認知症を伴ってくると、夜寝てくれないという悩みが出てきます。 我…